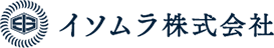各種道具類
ひと口に“道具”と言ってもその種類は無数と言って良いでしょう。一例を挙げてみます。
・面(おもて)・・・鬼 おかめ ひょっとこ 翁(おきな) 媼(おうな) 天狗 般若(はんにゃ)etc.
・武器・・・槍(やり) 刀 鉾(ほこ) 薙刀(なぎなた) etc.
・武具・・・鎧(よろい) 兜(かぶと) 帷子(かたびら) etc.
・履物・・・草履 下駄 草鞋(わらじ) etc.
・扇子・・・舞扇子(まいせんす) 祭扇(まつりおおぎ) 日の丸扇子 白扇 etc.
・被り物・・・笠 烏帽子(えぼし) 鳥兜(とりかぶと) etc.
・大物・・・神輿(みこし) 山車(だし) 屏風(びょうぶ) 纏(まとい) etc.
・その他・・・手ぬぐい たすき 鉢巻 行灯(あんどん) 提灯(ちょうちん) 注連縄(しめなわ) etc.
代表的な名称だけを挙げてみたのですが、実際にはその地方、舞踊の種類や発祥の年代に因って、形状や文様など千差万別です。
◆面
「おもて」或いは「めん」とも呼ばれるものは、大きさ、デザインから素材や塗装に至るまで、地域差が大きく、また上記の紹介にも書いた通り、色々な種類があります。例えば下のイラストのような天狗でも、表情だけでなく、ひげが描いてある物、植毛されている物と言った具合です。古くから受け継がれた物の中には、面の特徴を見て誰が打ったか分かる物も有ります。「どこそこの彫師の、先代が打ったものだと思うよ」と、写真を送っただけで言われる事も有るので、無くなる前に調べる事が大切です。

◆武器
昨今は若い方の中に、アニメなどのコンテンツの影響で、刀剣に興味を持つ方も多くなりましたが、刀は流派、時代に因って刀芯の反りや厚み、長さが異なります。槍も穂先の長さや形状が異なる物があります。武器にはそれぞれの流派流儀によって異なる仕様が有るのです。勿論現在の舞踊などに使用されるものは、重さやバランスも現代人に合わせて作らなければ、到底使いこなしきれないのです。しかし催事に使用されるとは言え、見た目だけでもその歴史に見合うものが良いのは当然です。

◆武具
こちらも武器と同様、刀剣と同様にTVやゲームなど様々なコンテンツに登場しますが、ご存知の通り鎧や兜は、その武将や家系によって形状が変わります。新調するにはかなりの費用が掛りますが、劣化し始めた場合、早いうちなら専門の職人によって修理出来る事もあります。もし使用されているものが有ったら一度チェックしてみましょう。

◆履物
ひと口に下駄と言っても、意外に形状はいくつも有るものです。高下駄も有れば、天狗で有名な一枚葉の下駄も有ります。白木仕上げや塗仕上げ等の仕様も様々です。またこれに属する物には、脚絆も含まれるでしょう。こちらは昨今製造メーカーが激減し、意外と手に入りにくくなってきています。逆に今でもそれなりに手に入るのが草鞋(わらじ)です。川の流れに入って魚を獲る漁師さんや、釣り人にも利用される為、まだ手に入れる事が出来ます。

◆扇子
京扇子、江戸扇子と言った今でも日常で使用されるものも、舞扇、祭扇等、骨の数や扇面の大きさが異なる物がかなりあります。国内で生産できる職人はかなり減ってきており、一部のお客様からは関東で、誂え扇子を頼めるところが殆ど無いと言われたことが有ります。今や扇子の柄もデジタルデータで入稿する事が必須となってきました。扇面が劣化すると再現が難しくなりますので、早めに作る事をお薦めします。


◆大物
神輿や山車は祭の花形的な存在と言って良いでしょう。しかしこれを新調するには1000万円を超える費用が掛る事も多々あります。傷んできた個所を早めに修理する事が肝心です。製作した職人さんがいれば早めに準備して依頼しましょう。もし既に依頼できなくなっている場合でも、修理する事の出来る職人はまだいらっしゃいます。素人細工では逆に悪化してしまう事も有るので、絶対に無理をせずプロに任せましょう。お正月に見掛ける獅子舞い。この獅子頭も神輿などと同様に修理することができますので、御問い合せください。
屏風や纏も職人の数はかなり少ない状況にあります。ある屏風工房では同じ内容の御見積依頼が、一度に6件来たことが有るそうです。実は自治体からの依頼品の入札だったのですが、地元で作れる業者は全て廃業しており、巡り巡って行きついた先は全て同じ工房だったのです。それほどきちんとした技術を持った職人は少ないのです。


◆たすき・鉢巻・その他
シンプルな構造のものは、染物、織物や描き物と、何でもありと言えます。たすきや鉢巻は単色無地の物から柄の染め抜かれた物がいろいろあります。刺繍やジャガードと言った、手の込んだものもたまに見かけますが、かなり少なくなっています。提灯は手描きの物は、かなり職人さんが減ってきているので、最近はデジタルで出来るようになってきています。
また一部の民俗舞踊に使う装束の中には、多色染めの物が多く存在します。これらは以前には多数の地元業者様に因って、手工業で生産されていたものが多く、中には手描きのものも存在しました。しかし、昨今は激減し小ロット生産が難しい物も増えています。
上記のような物も比較的小ロットの生産を出来る限り追及しています。素材を変更、あるいは染色方法を変更する事で最少ロットを出来るだけ小さくするよう心掛けています。
小物類は手甲や脚絆、笠など、種類が多く全てを記載しておりませんが、写真などから復刻複製が可能かご相談頂く事が出来ます。