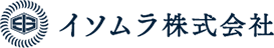★作りたいのはどんな幕?どんな旗?
幕
ひと口に“幕”と言っても、様々な種類があります。幕の種類に因って、染めるもの、織るものに分かれ、また更に刺繍を施すものも有り、図案や現在お手持ちの物を拝見してご提案をしていく事が多いです。製作にはかなりの御時間を必要とするケースが多いので、復刻をご検討の際には余裕を持ってご相談下さい。
◆寺社幕 奉納幕
神社や寺院の本殿入口などに掲げる横に長い幕。基本的には染め物と考えて良い。稀に刺繍が施されたものも有る。寺紋、社紋、家紋等とそれを納めた年号や寄贈した個人名や会社名などを染め抜いた物が多い。

◆懸垂幕
縦に長い幕で、山門の軒下から吊下げるなどして使用される、大型の幕。祭禮を始め寺社で催される行事名等を染め抜いたものに多く見られる。

◆祭礼用の各種幕
山車に使われる中で、一番上の高覧幕、メインとなる中幕、車輪の上部を覆う腰幕、山車に乗るお囃子の奏者の後ろに有る背幕などが多種有る。刺繍や染め物の他に、昔は綸子地(同色の糸で柄を織り出した生地)ものも有ったが、現在は別注可能な織元はほぼ消滅していると言って良い。地域によっては御神輿の下段に巻かれている腰幕もある。
◆各種舞台幕
演壇の後ろを取り巻くように飾られる物を始め、演出に使用する様々な幕が有る。染物、織物とも作られる。
旗・幟(のぼり)・暖簾(のれん)
小さなものは「比礼旗」等のタオルより小さなものから、大きなものでは長さ10m以上、巾1m以上も有る巨大なものもあります。素材も木綿、正絹などがあり、柄の表現方法も各種染色は元より、先染めの糸を使う織柄など多彩です。復刻にとても時間が掛り数ヶ月以上掛る、複雑で精緻な柄のものも有ります。また旗と言うのは一般的な国旗など横長をイメージする方もおおいですが、ここで作られる旗は縦長の物が多いのも特徴と言えます。
◆旗
祭禮に登場する猿田彦等が持つ比礼鉾に付いている小型の旗の比礼旗(ひれはた)を始め、萬歳旗、霊鵄八咫烏旗(れいしやたがらすき)や、サイズも色柄も地域によって異なる社名旗(神社銘が染め抜かれたもの)等多種多様で、先染めの織物と染め物の双方が有る。受け継がれているものを拝見すると、既に織る事の出来ない生地や、正絹等の現在では非常に高価な素材で作られている物もあり、完全復刻ではなく、素材等を変更し複製することも考慮する事が大切。

◆幟(のぼり)
幟とは縦長の生地の上と横の片側に「チ」或いは「チチ」と呼ばれる竿通しの輪が付いている旗の一種。小さなお社の鳥居横を飾る真っ赤なのぼりもあれば、神社の名前や祭禮の名前を染め抜いた長さ6間(約10.8m)、巾3尺(約90cm)と言う大きな物などもあり、多岐に渡って使われている。街中で見かける交通標語やお店のアイキャッチに使われているものの多くは、ポリエステルポンジー等の化繊にプリントしたものが大半だが、大型の誂えには帆布や葛城と言った、綿の厚地が扱われており、数十年以上継続使用されるものが多々有る。古くは墨を使った手描きの物が中心だったが、現在は両面顔料プリントで作られるものが主流となっている。幟には文字が中心になっているものが多いが、その書体は特徴的なものが大半で全てトレースが必要となる。

◆暖簾(のれん)
のれんと聞いた時に、台所を思い浮かべる人は昨今は減ってるかもしれない。ひと昔前はご家庭でも見かけた暖簾だが、今はリビングダイニングが主流となって台所と居間、今で言うキッチンとリビングの境が曖昧なためあまり使われなくなっている。それでも脱衣所や洗面所の入り口に目隠しとして、家庭の中でも使われているケースもある。ここで言う暖簾は上記のような家庭で使う物だけでなく、店舗や寺務所、社務所の前に使う日除け暖簾等の大きなものをメインに、各サイズに対応して様々なものを製作している。
暖簾は現代風に言えばパーテーション。空間を仕切る事、視線を遮る事、更に日除けや風除けを目的に、色々なものを染め抜いている。家紋や屋号等がその代表。また芸能の世界で良く知られるのは楽屋暖簾である。「○○さんへ〜□□一同」と染め抜いた物を贈られる事も多いので、歌舞伎などを特集したTV番組などで見かけたことが有るのではないだろうか。