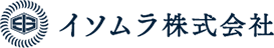★作りたい衣装はどんなものでしょう?
染め物編
現代の染色方法はたくさんの種類の技術が使われています。昔からの染色方法に、最近はインクジェットプリントも色々な場面で使われるようになり、若干ではありますが価格も安価になってきました。それをデザインに因ってどう使い分けるか(※1)のご提案が正しく出来る事が、伝匠堂の腕の見せ所です。
※一部の製品は染め物と織物、どちらでも製作できる旨をご案内しています。

長年使用されていれば、どんなに丁寧に保管していても、経年劣化で傷みます。
失う前に残していく対策をしましょう。
御見積はこちらから
◆半纏・法被
祭半纏、印半纏(寺社、店舗、サークル)等、象徴的に使われてきた半纏。
「柄が特徴的、色がちょっと変わっている、他所ではあまり見かけない」
と言う物が多く、市販品に少し加工したくらいでは作れないものが多い割に、それを作り直したいと思っても、生地の種類が分からなかったり、職人や工場には得手不得手があり同じ物を作れる業者が見つからなかったりと、苦労をした方も多いのではないでしょうか?
伝承堂では染色や加工方法も柄に合わせ選べます。(※1)
・反応染−片面染 両面染
・顔料プリント
・インクジェットプリント
・本藍染(鉱物染料ではなく、藍草を発酵させた古来からの藍染)
・引き染(主に正絹)
・ジャガード織(柄を浮き出させる織物)
※半纏にはこれまで織物は殆どありませんでしたが、染めでは再現しきれない特殊なものを、ジャガード織で作る為、例外的に染め物編の中に記載しました。
これら多種の職人や工房、織元などと手を繋いでいますので、殆どの半纏を復刻出来ます。

▲知っている?「半纏と法被」
半纏と言う名称は関東以北で多く使われ、法被(はっぴ)は関西以西で多く使われると言われます。本来は形状が若干異なっていましたが、江戸末期以降からほぼ同様の形になり、現代では基本的には全く同じ物と考えて大丈夫です。
法被は、古代の胴衣の一種ではんぴ(半臂)と言う名称が、その由来と言われています。
半纏は、“半反で纏える(まとえる)もの”、つまり反物1反の半分で作れることが、その名の由来と言う説が有力です。
※諸説があり、一般的な解釈とされている内容です。
御見積はこちらから
◆浴衣
浴衣と言えば、盆踊り、花火に縁日と、着ていく方も少し増えてきたこの頃ですが、やはり有ったら良いなと言われるのが
「揃い浴衣」
でしょう。揃い浴衣は町会等の自治体の盆踊りや踊りの会、最近は高校や大学の文化祭と言ったイベントなどで、現代風のデザインも取り入れて作られています。また昔から同じ柄を受け継いでいるものも数多く残っています。古典柄には色々と素晴らしいものがたくさん残っていますが、製作当時の技術は既に失われ、昨今の工房では既に再生できないほど手の込んだものが存在します。それを今の技術を駆使し職人達が復刻してくれます。総柄(同じ柄が繰り返し染められている物)と、絵羽柄(仕立て上がった時に肩から裾に掛けて1つの柄構成になっている物)と、双方に対応しています。
こちらも半纏と同様、様々な染め方で作れます。
・注染
・反応染−片面
・本藍染
・顔料プリント
・インクジェットプリント

御見積はこちらから
★作りたい衣装はどんなものでしょう?
織り物編
祭禮や伝統芸能の衣装は織物が多く使用されています。但し同一の織物が再現できるケースも、再現できないケースもあります。厳密には大概の織物は再現出来る(※2)のですが、その費用が膨大になる事が多く、類似製品を製作するケースも多くなっています。
◆狩衣
「かりぎぬ」
この衣装は平安時代以降の公家の普段着。元々は狩の装束として生まれその機能性から通常時にも使われるようになったと言われています。その後武家の比較的高位の礼服、更に後世は神職の装束としても使われた事も有り、各種の伝統芸能の衣装となっています。しかしその形状は地域や発祥の時期に因って、少しずつ異なっている事も有り、復刻には専門の知識と技術を要します。伝承堂に繋がっている職人さんには、これらの専門家もいます。劣化し原型を失う前に是非復刻し、受け継がれているものを大切に史料として保管管理して下さい。
 写真は既製品です。
写真は既製品です。御見積はこちらから
◆直垂
「ひたたれ」
この衣装は主に武家社会で用いられた男性用の衣服で、狩衣よりも更に高位の礼服でもあったものです。その発祥は古墳時代とも言われ、伝統芸能に使われているのは至極当然と言えるでしょう。これも古くから受け継いでいるところが多々あり、修復が困難なものもあります。一度失ってしまえば復刻が困難なケースも有ります。どうか早目にご相談下さい。
 写真は既製品です。
写真は既製品です。御見積はこちらから
◆袴
「はかま」
日本で古くから使われていて、あの古事記や日本書紀にも既に記述があると言うもの。つまり日本史をひも解いて袴の無い時代を探すのが難しい程ですが、形や使用方法はその時代で色々な変遷をしており、定義付けは難しいと言って良いでしょう。袴に分類される衣装の数は両手に余るもので、当然伝統装束として受け継がれている物も、どれに属するか判断するのは考古学の先生にお任せしたいレベルです。袴は現代で使用されるものには染め物が多数あります。色柄は元より、仕立仕様も同じ物が少ない為、「はかま」と言う言葉の知名度と逆に、失うと再現がしにくいので注意が必要です。「袴」の文字が付く物を一部挙げても、
「行灯」「馬乗り」「たっつけ」「武道」「表」「水干」
などがあり、同じ名前の物でも前述の通り、実際の形状が異なる物が複数有るのです。
 写真は既製品です。
写真は既製品です。御見積はこちらから
◆帯
これは言い換えれば、身体に巻き付けて使う物の総称と言って良いでしょう。つまり用途によって形状も素材も、サイズ、柄等、異なる物が無数にあります。「所変われば品変わる」と言うしかないのです。ご当地のみで常識になっているものがかなり多く、御依頼の中には「普通の帯だよ」と言われて、サイズとデザインを伺うとかなりのレアものだったと言う話は、枚挙にいとまが有りません。殊にその土地では、以前特産品としていたと言う素材が使われていると言ったものは、意外とレアなものが多いように感じます。
半纏帯、浴衣帯は既製品を使っているケースも多いですが、伝統芸能の装束には特定の柄や形状の物が使われている事が殆どです。染物と織物、どちらも対応しています。

御見積はこちらから
◆たすき・鉢巻・その他
装束にも分類される小物も多くありますが、詳細は「ふっこく 各種道具類」のページにてご案内しています。
※1
▲染色方法とその特徴
・注染・・・古くから使われる染め方で、綺麗に裏抜けし、柄のアウトラインが柔らかな染色方法。あまり細かい柄は不向き。綿を染めるのに向いており、浴衣、手ぬぐいは今でも注染にこだわる人は多い。
・反応染・・・反応染料を使い、7〜8割の裏抜けがある。再現性は後述の顔料プリントと同様でかなり高い。幾何学模様などを染めるには特におススメ。和装、洋装を問わず、現代で最も多く使用されている染色方法。
・本藍染・・・昔は使い込んだ浴衣を解き、赤ちゃんのおしめにも使ったほど、肌にも優しい天然染料。8割以上裏抜けする。半纏や浴衣の最高級染色方法と言える。使い込むと色が変わり、独特の色の変化を見せてくれる。(色が冴えるとも言います)
・引き染・・・刷毛を使って下絵に沿って、色を染めていく技法。呉服用の反物を始めとした、正絹を含む高級品に多く使用される。職人の腕が出来の良し悪しを左右する。
・顔料プリント・・・裏は真っ白だが最近は技術が進み、フルカラーも可能。印刷のようにかなり細かい柄、細い線も再現できるのが特徴。インクジェットよりもやや安価だが、堅牢度はやや低め。
※令和4年頃から更に技術が改善され、再現性はインクジェットプリントを凌駕するものも出始めた。
・インクジェットプリント・・・裏は真っ白だが、再現性は他に類を見ない。もちろんフルカラーに対応。古来の注染で、現在は再現できないような多色のデザインも、これならば再現が出来る。
御見積はこちらから
※2
▲織物の複製
伝匠堂では、様々なものを複製や復刻する事が出来ます。その中で織物の複製は技術的には可能なものが多々あります。しかしここには大きな壁が有るのです。それは費用です。
現在の織物と江戸時代以前の織物の、最も大きな違いの一つが生地巾です。昔の織機は基本的に小巾用、つまり織り上がった生地は1尺(約30cm)〜1尺5寸(約45cm)前後。現在は110〜130cm前後の広巾生地が主流となっています。生産効率が良い事や、大きなものを作る時に裁断縫製を減らしコストを抑える事が出来るからです。そして殆どは平織かそれに近い物です。
ところが古くから受け継いで来たものは、当然小巾で織られており、小巾だからこそ細かい柄を何色もの色糸を組合せて織りで柄を出す事が出来ているのです。必要な色の糸を先に染めて、柄を織り出すので「先染め物」とも呼ばれます。
以下が完全再現に必要な条件です。順に見ていきます。
1.小巾の織機
数は少ないですが、一部の工房がまだ維持してくれています。部品の補充も需要が少ない為かなり高価で、使用せず維持するだけでも大変です。
2.紋紙
経糸を通すパンチカードのように穴が開いた紙のこと。柄に合わせて、1反分で数百枚、多いものは1千枚を超え数十キロを超える重さになる紋紙を作る必要があります。
3.色糸
柄に必要な色数だけ必要ですから、柄が繊細になればなるほど、染め分けた糸が必要です。どんなに小さな部分も色が違えば用意しないわけにはいかないのです。
4.技術
細かな柄の織出しは機械が自動で出来るものに限界があります。ミリ単位或いはそれ以下の微調整が柄の輪郭や全体のイメージを作るので、手作業で修正をする必要が有ります。
織物の完全復刻、完全複製に膨大な費用が掛る事があると言うのは、この条件を全て満たす必要があるからです。たくさんの工房と手をつないでいると、「その柄の紋紙、あそこの織元にあるよ。」と言われることが時折あります。そうです、昔から受け継いでいて保管管理されているものと同じ柄ならば、この紋紙代は要らなくなるのです。繋がる工房は多い分だけ節約できる可能性が広がり、受け継いできたものを寸分違わず再現出来る可能性もあるのです。当然その織元が廃業、職人が引退をしてしまうと、当然失われてしまうのです。